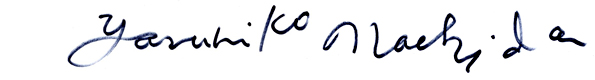隠れることを好む
土曜日, 27 7月 2019
方丈記私記[平成]No.016
紀元前500年前にヘラクレイトスが「万物の根源は火である」と言うそのさらに前に、タレスという人が「万物の根源は水である」と言ったそうだ。ヘラクレイトスはタレスの死後に生を受けているから両者が言葉を交わしたことはないはずなのだけれど、こうやって並べて記述されたそのとたんに「場」が生成され、まるで彼らが言葉を交わしているように思えるから不思議である
万物の根源を火に見たヘラクレイトスは、こんなことも言っていたようだ、「ピュシス(自然)は隠れることを好む」と
ピュシスは(好まれて)隠れているということで目にも見えないから手に負えず、けれども「それ」が目に見えてくるのを待って「そこ」に留まるのも退屈だから、とわれわれは待つのを止め「そこ」から新大陸を求めるように勇んでススンできた。そして今に至る道を選んだわけだけれど、選んだ道の先にあったのがロゴス(理性)だったのか、観念主義だったのか、主観主義だったのか、経験主義だったのか、実存主義だったのか、近代主義だったのか、そんなことに私はあまり興味がなくってむしろ長いなっがい道程を振り返りながらもわれわれの遥か後ろにおいて置かれた「そこ」こそが今たまらなく気になっている
私が住む森の中で、たまたま木が倒れる瞬間に立ち会ったことがある。特に風が強かったわけでも、湿った雪が枝葉に積もっていたわけでもなかった。一見して特に外因があって倒れたわけでもないその木は、人間の年齢でいうと幾つくらいになったのだろう、他の木の影に入るような幼木ではなかったし死に絶える直前の老木でもなかった。いつだって倒れる可能性はあったにしてもその時に限って倒れる理由などあったようには見えなかった。何年も風雨に耐えてきて、それは、私には見えないタイミングを待って、倒れた
ピュシスが隠れることを好むのなら、人間の私にはピュシスは「死」を隠しているように思えてくる。だってジッサイに人間として生きるわれわれはだれひとりとして死を、死ぬというコトを知らないのだから
またしても映画の話になる。人の、生きていることと死んでいることの境、その境に流れる川をただ静かに見つめるような『眠る男』という映画が平成8年に公開された。映画の主人公である眠る男タクジは文字通り植物のように寝て横たわったままである。私が森の中で見た木は倒れただけで死んだわけではなかったわけだけれど、それと同じことで、タクジもまた寝たままに生き続けている。映画の冒頭部のシーン、水平に眠るタクジという男のすぐ上に、花をつけた白梅ととても大きな満月がぽっかりと浮かんでいる。ひとはこんなにも自然物と近いのだよ、と観ている者はそのジジツを優しく伝えられる。眠る男の眠る部屋、いや、ルームと呼ぶにはかなり躊躇ってしまう、ただ「場」と名指すしかないその場所に扉や窓はひとつもついていない。限られたものと限りないものとの境としてではなく、限りないものと限りないものとの境としての身体が、扉としてある。しかもその扉は、目や鼻や口などの感覚器官がそうであるように、つねに外部に対して開け放たれている。タクジの耳はずっとずっと自然の音を聞いていて、タクジの鼻はずっとずっとその匂いを嗅いでいる。映画の始めから終わりまで絶え間なく川の流れる音が聞こえていたような気になるほど、画面に水がゆき渡っている。そして、私は、というと、それら一切合切をタクジと共有したのだ、と映画が終わり、音が途絶えてから知る。映画を観ている私こそがタクジだったのだ、という気すらしてくるのだったけれど、でも、そういったことですら、つまり川の流れる音を聞いたりそれらから何かを想起したりすることすべてが動物である「人間」のすることだ、ということにしみじみと行き当たる。私は確かにタクジ(自然物)だ、でも、私はタクジ(植物)ではないのだ。映画は、私を突き放すようにして動物である「わたし」にとどまるよう呼びかけているようでもある
われわれは、タレスやヘラクレイトスの時代からいち、に、さんと数えられる歴史の時間よりももっともっと長い時の間、動物であることを結局はやめたりはしなかった
(好まれて)隠れたピュシスがでもいつでも「そこ」にあることを、タレスやヘラクレイトスは動物であるところの「身」をもって知っていた。いや、われわれだって動物であるところの「身」をもっているわけだから本当は「そこ」にあることを知っているはずなのだけれど、彼らとわれわれとの間に深い溝があるとすれば、それは、知っている、というそのことを彼らがいっときも忘れることがなかったのに対して、われわれの方と言えばもうずっと長いこと(生命の歴史から考えればほんの束の間なんだけれども)、その知っている、ということをすっかり忘れてしまって「ここ」にある、というジジツに違いない。そもそも万物の根源へと遡行するその意識が万物に包まれていることを知っていなければ、「万物の~」と言いはじめることなど出来ないはずで、「万物の根源はエネルギーである」とわれわれが言う時に、われわれは、それをジッサイには「考えて」もいないしましてや「感じても」いない。つまり「万物の~」と語り始めて何かを知ったようなフリをするわれわれの「身」は万物の側にあるのではなく、あくまでも「わたし」という主体の側にある。そして、わたしが主体の側にあるというそのことに関しては、なぜだか熱に浮かされたように強く主張し、そして、信じて疑わないのだ