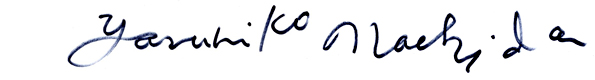方丈記私記[平成]No.023(完結)
「コロナの感染者数」を数えるのに忙しくしている間にも、人は違う感性で東日本大震災から10という年月を数えていた。その10という数字をどのように捉えるのかは人ぞれぞれだけれど、私自身はがらがむしゃらに生きてきてちょっと感慨深くいて、令和3年の3月11日は特別な過ごし方をしたいような気がしたのだった
阪神淡路大震災の時は祖母が神戸で被災して「大変だ、大変だ」と私も現場に駆けつけカラ騒ぎしたけれど、あの日から積み上がっている年数は私の中ですでに白濁として定かではない(平成7年1月17日から冷静に数えれば26年が過ぎていると振り返ることはできる)。西ノ宮で生き埋めになった祖母が昨年100歳に達したことを(コロナ禍なのでオンラインで)親戚一同で祝ったけれど、もはや阪神淡路大震災は祖母の人生の中で数ある出来事のひとつとして処理され色褪せてしまっているのかもしれない。私も東日本大震災が起きてから数字を足していき、同じようにいずれはそれが記憶の中で薄くなっていくことは目に見えていて、でもそうなった時、私はどこでどんな生活を送っているのかと彼女の顔を見て不思議な気持ちになった。100歳とは言わないまでも60歳くらいになっていて、孫に還暦のお祝いをしてもらったりしていることもあるのだろうか。なんとなく、60歳まで生きることを前提にしてものを語ることの難しさを、今、感じている。どちらにしても「あれから何年」と311から数字を勘定しているのはジジツとして、正直なところ、度重なる災害や人災が降りかかるその都度それぞれを必死になって切り抜けるしか道はなく、まぎれて大震災の記憶は薄まりつつある。つまり、おそらくそれをジッカンしているからこそ、10という数字の節目においてどこでどう過ごそうかと改めて考えようとしたわけなのだ
そして、個人的な(内面の)揺れが他人の揺れに同調してしまう時間をあえて過ごすより、個人的な揺れは個人的な揺れとしてしっかりと感じていたいと思ったから、色々と考えて、震災直後に訪れた南相馬の喫茶ウェリントンでコーヒーでも飲みながらひとり過ごすこととした
「喫茶ウェリントン」ここにそう書くだけで感慨深いものが湧いてくる
映画を撮るための視察を兼ねて津波が襲った地域を車であちこち走破したのが2011年の春だった。相馬は、漏れ出る放射能による影響で立入禁止区域が網の目状に伸びていたためアクセスが難しかった。宮城県の方へとぐるっと迂回しつつ北から降りるようにしてどうにか立ち寄ることができたのだけれど、ちょうどお昼時なのに空いている飲食店はほとんどなくて(もちろんそうだろう、多くの住民が避難したわけだし観光客などいるわけはない)、それでもどうにか営業していた店が喫茶ウェリントンだった
一種独特な空気が充満していた当時の福島にあって、生活の匂いがするその喫茶店を見つけ吸い寄せられるように中に入って、私は、救われる思いがしたのだった(※1)
それから、私は喫茶ウェリントンを再訪できずにいたからほぼ10年ぶりにお父さんが入れてくれるコーヒーを飲むことになるはずだった。だった、と書くにはもちろん理由があって、結論から言うと店はもうなくなっていた。同じ場所には、真新しい南相馬市民文化会館が建っていた。現地でネットを使って調べると、立退があった後も喫茶店は一度位置を変えて営業を続けたようだけれど、2年前にその店も(別の人が経営する)カレー屋に取って代わられた。私はもっと早くに再訪できなかったことを小さく悔いたけれど、なくなってみて、10年という年月の長さを改めて思い知った。あの時は喫茶ウェリントンだけが店を開けていて、今は、あらゆる店が営業しているというのにウェリントンだけが姿を消してなくなっている。10年前、私が「ウェリントン(※2)には行ったことがあるんですか?」と女将さんに問うと、顔を赤らめながら「行ったことがないんです。でもいつかは行ってみたいと思っているの」と返事をしてくれた。今、喫茶店をやっていた夫婦がどうしているのかはわかりようがないけれど、喫茶店をやめていの一番でウェリントンへと旅したことを他人事ながら期待する。そして、許されのであればいつか彼女たちの旅の話を聞いてみたいと願う。今、コロナ禍で、海外へと行くことのハードルは随分と上がったように感じるからなおさらだ
それはそれとして、「2時46分」を時計の針が通過するその瞬間を過ごすべく場所の当てがなくなって、私は、途方に暮れた。海でも見ながら、とも思ったけれどそれはそれで私の揺れとは違う「波」に同調することになるかもしれず、どうしようか、と考えあぐねながらとにかく海の方向へと車を走らせていると、桜井古墳群なる遺跡に出くわしたのだった。時刻も迫っていたから「せっかくの出会いなので」と、迷わず私は前方後方墳の上に立った
長さが75メートルある東北最大級の墓の上に立つと、四方がしっかりと見渡せて「ここでよかった」と胸を撫で下ろした。西には喫茶ウェリントンがかつてあった町の賑わいが感じられ、その先に阿武隈山地が臨めた。南には別の町の賑わいがあり、北には新田川とそれを利用した水田が広がっているのが見えた。そして東には川が流れ着く先の太平洋がかすかに見えた。いや、つまり、人の営みに関わる全てのものがここから見渡せたのだった。私は、新田川の流れを見ながら茫々とした意識で、土地に、ほんのひとときに現れるひとつの生活の儚さ、みたいなことを感じていた。喫茶ウェリントンは私の世界に現れて、そして幻だったかのように綺麗さっぱりと世界からなくなった。きっとどの時代のどんなものも、誰かが軽く瞬きをするような感じで、あることとなり、そしてなくなる
しかしそう感じる私は4世紀に建てられた墓の上に立って、古代の人も見ていた新田川を現代に見ている。それは紛れもなく同じ川で、その流れは絶えずあったはずだ。しかし、くどいようだけれども、そう、そこを流れる水はしかしもとの水ではない
「ウーン」と方々から一斉に汽笛のようなサイレンの音がこだまして、私は、きっかり令和3年3月11日2時46分に、我に返った。「我」に返った私はその時、でも、誰の目でもいいような目を瞑り黙祷を捧げ、誰の耳でもいいような耳で風や鳥のさえずる音に混ざるサイレンを聴いたのだった
・・・・・・・・・・
今まで平成に起きた災害や人災による死亡者数や被害の数を記してきた『方丈記私記[平成]』だったわけだけれど、最後を締め括るのにそれらとは違う「何か」を数えたくなっていた私は、「喫茶ウェリント」までの道程で渡った川の数を数えることとしたのだった。そのいたく個人的な記録を残し『私記』を終わりにしようと思う。相馬に向けて益子町を出発した私が渡った最初の川は隣町を流れる逆川で、そこから数えて84の川を渡り南相馬に辿り着いた。ひとまずどんな太さの川も「ひとつ」と数えたけれど、見落としたものもひとつやふたつあるかもしれない。世の中に名前のつかない川があるのか知りもしないけれど、渡った川で名前を知ることができたものをここに書いておく(本流、支流を含めて複数回渡った川の記載は1度とする)
逆川、那珂川、大沢川、緒川、玉川、久慈川、浅川、山田川、里川、入四間川、十王川、小石川、花貫川、多々良場川、関根川、塩田川、大北川、江戸上川、里根川、蛭田川、豊川、鮫川、渋川、藤原川、釜戸川、藤原川、矢田川、滑津川、夏井川、横川、小久川、大久川、折木川、浅見川、木戸川、井出川、富岡川、熊川、高瀬川、請戸川、宮田川、小高川、前川、太田川
川の数を数えることなどにもちろん意味はない。意味などないけれど、その意味のなさに安堵している私が確かにここにいる。あらゆるものに意味がないことを受け入れつつ生を開いていくのか、それとも何かしらの意味が得られることを信じてゼロから数字をひとつひとつ積み上げていくのか、そのふたつの道はそれほどまでにも違ものなのか。そもそも、数字を積み上げることを受け入れるそのことこそが生活ということなのかもしれないとさえ思えば、私は、この世に生を受けていったい何をしているのだろう、自分のことだけれど、まったくわからない。わからないからひとまず数字を数え上げるけれど、やっぱり何度も挫折して「無理だ」と私はゼロへと落ちていく。ゼロへと落ちていく時、私は、、、
その時、心はさらには答えなかった。そうであるならば、、、
今はただ、答えない心のかたわらに、つかの間の舌のちからを借りて、心のあずかり知らない南無阿弥陀仏を、三べんほど唱えて、この暁(あかつき)の随筆を、静かに終わりにしようか。
これは、鴨長明が『方丈記』を締めくくる時に書いたことである
そして『方丈記私記[平成]』に、私が最後に書いていることである
(※1)その時のことを『喫茶ウェリントン』という文章で「ミチカケ」に発表しました。noteにもアップしているのでもしよかったら読んでみてください
(※2)ウェリントンはニュージーランドの首都