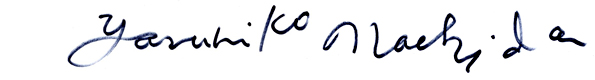音の孤独
月曜日, 15 8月 2011

老舗のデパートの外壁を色取る国旗が風を受けてへんぽんと翻っている。ホシムクドリの体に浮かんでいる星が小さな四角い青空にも同じように散らばっている。動きをもらった赤い直線のストライプが、静かに眠る森の住人を煽っている。
祖父は、静かにこう話し始めた。まるでそこが戦場で、私が敵に見つかってしまうことを怖れているかのように。
「私はいつ死んでしまうかわからないから、このことだけは話しておきたいとずっと思っていたんだよ」(『ハトを、飛ばす』本文より「音の孤独」)
祖父が語った戦争の記憶は、私の側の言葉とは分離して、語られたときのまま、国旗を揺らす風の届かぬ底に今も沈んだままでいます。